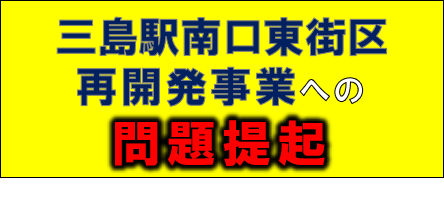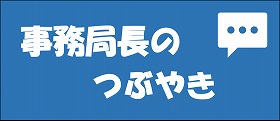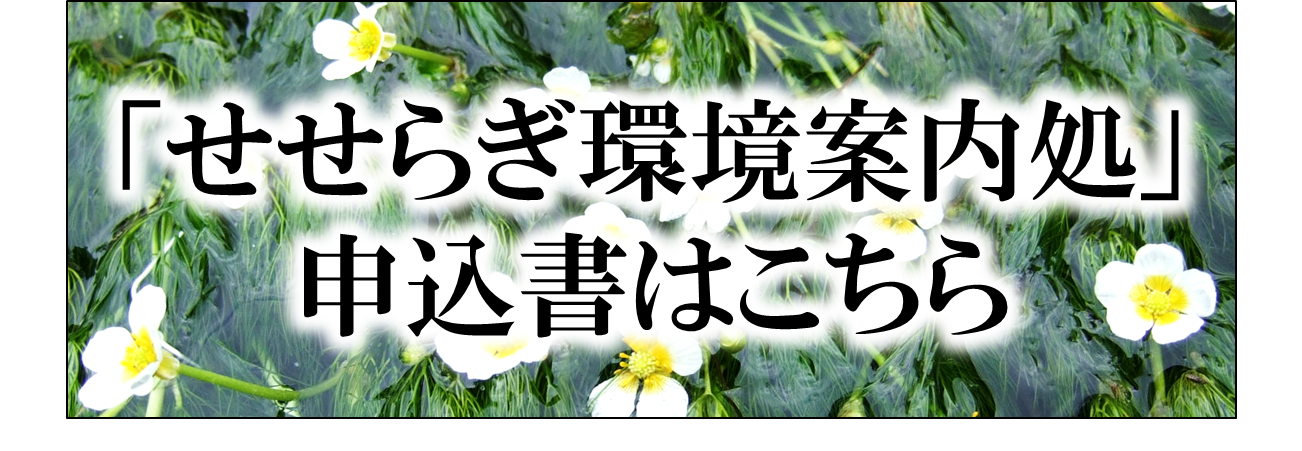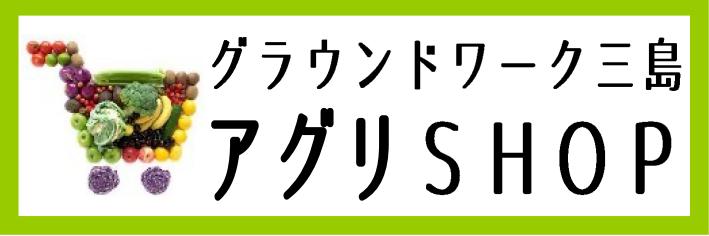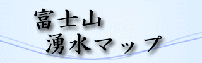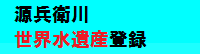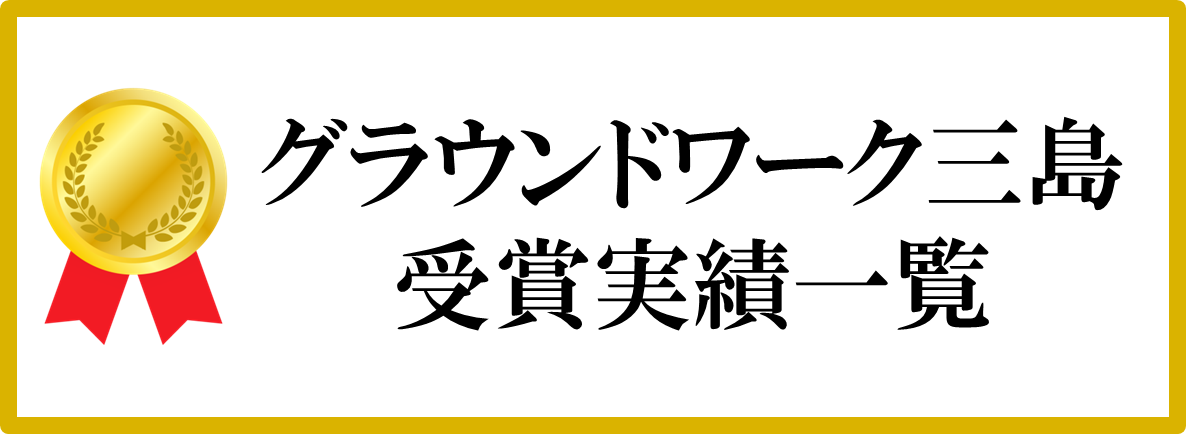令和2年5月3日佐野美術館「三島梅花藻の里」の様子を見に行ってきました。何と富士山からの湧水量の増加に合わせ水中花の白い花々が満開で咲き乱れており、その迫力に感動しました。水車のポンプ調整やヌクの排除、噴水の清掃など、気づいた範囲での整備・点検・調整を行いました。
しかし悲しく、辛い現場を目撃し対応に苦慮しました。水源の池に何組かの親子が来ていて魚を捕獲し、池の中に入り泥水を発生させていました。注意看板があるのですが、気づく振りもなく親からの注意もなくやりたい放題です。意を決して注意しようとしたらバタバタと帰りいなくなってしまいました。
池にいたほとんどの魚を捕まえてしまいましたが、自宅に持ち帰っても数日間で死んでしまいます。人為的に造られた水辺環境であり、人々の生き物たちへの愛情と思いやりの心、ルールの尊守、親の教育などが無いと適切な保護保全に限界があります。
10年以上もの間「環境出前講座」を開校し、自然との共生の知恵とルールを毎年2000人以上の子どもたちに環境教育してきましたが、まだまだ不充分だと実感しました。魚は死んだら捨てられるだけです。この非情な現実を親はなんと考えているのでしょうか?


三島産新銘柄米「ゆめみしま」のご購入はこちら
「2020年アジア都市景観賞」を受賞しました。
2024年4月26日「ミシマバイカモ見頃」の記事を掲載
グラウンドワーク三島のfacebookページ
グラウンドワーク三島のインスタグラムページを開設しました!
イギリス&日本・自然環境回復の処方箋~グラウンドワーク~
A story of Genbegawa
2021年8月26日「三島梅花藻の里」の定例整備作業
2021年9月16日「桜川川端」の整備作業
2021年8月28日「鎧坂ミニ公園」の整備作業