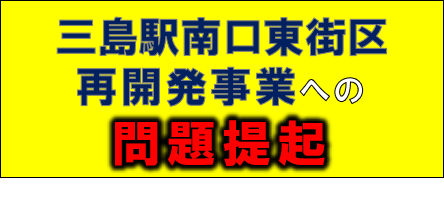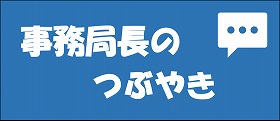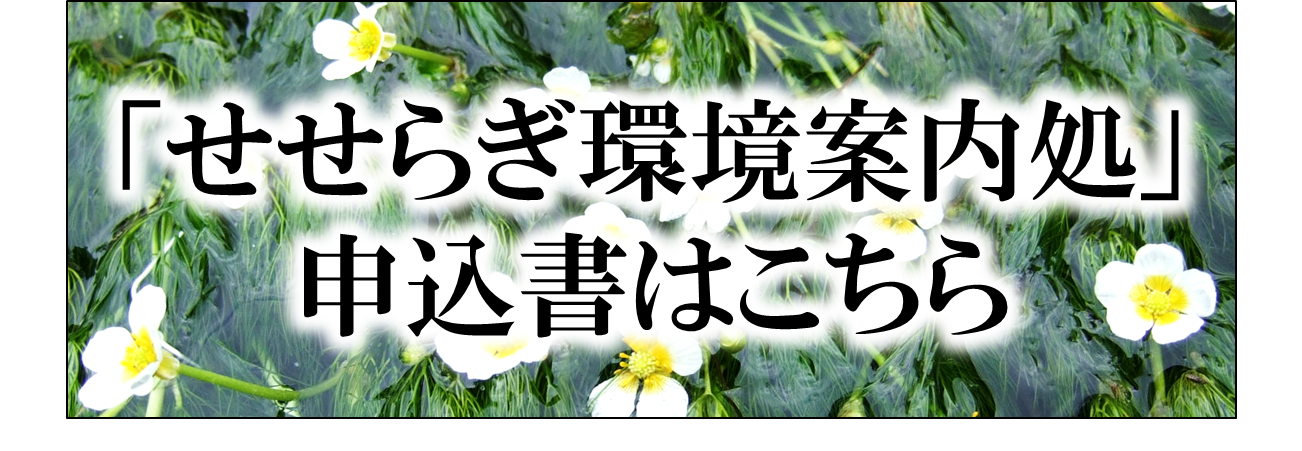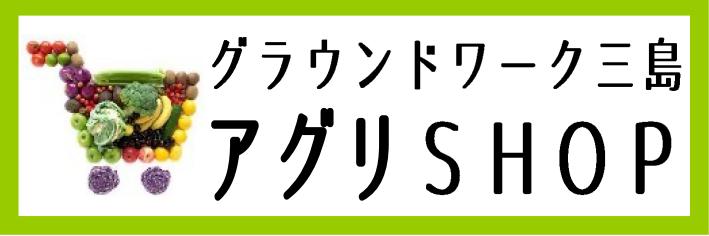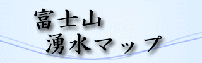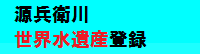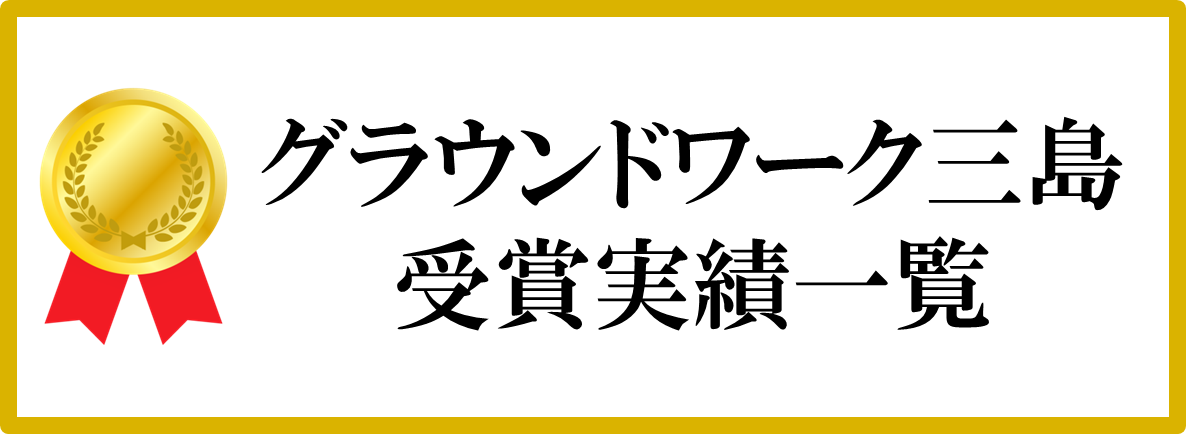窪の湧水
|
長泉町竹原地区の「窪の湧水」(別名小僧池・富士湧水池)は、江戸時代の安政元年(1854)11月4日の大地震によって湧出が始まったとされる湧水池です。伏見窪に位置することからこの名がつきました。 |
 |
|
この湧水は、本宿村や伏見村の農業用水として利用され、大正7年(1918)には、特種製紙株式会社の前身である高野製紙所が、これを取水して操業を開始しました。当時、湧水量は毎分8トン(日量12,000トン)を超えていました。 「窪の湧水」は、標高20メートルの段丘崖の下部から湧き出す湧水で、その段丘崖には、はるか昔の自然植生をしのぶ貴重な照葉樹林が残っています。 |
 |
|
地域の貴重な湧水池として、また自然とふれあう場として愛されてきた「窪の湧水」を、特種製紙株式会社、関係自治会、長泉ホタルの会、NPO法人グラウンドワーク三島等が協働し、斜面の安全性に配慮しながら、ホタル等の生き物のすみかに適した整備を進めています。 |
 |
メニュー
アーカイブ
三島産新銘柄米「ゆめみしま」のご購入はこちら
「2020年アジア都市景観賞」を受賞しました。
2024年7月25日「台湾社区大学・三島研修」「ネパールの中学生・環境保護活動を体験」の記事を掲載
グラウンドワーク三島のfacebookページ
グラウンドワーク三島のインスタグラムページを開設しました!
イギリス&日本・自然環境回復の処方箋~グラウンドワーク~
A story of Genbegawa
2021年8月26日「三島梅花藻の里」の定例整備作業
2021年9月16日「桜川川端」の整備作業
2021年8月28日「鎧坂ミニ公園」の整備作業
サイト内検索
検索は2文字以上で
コメント